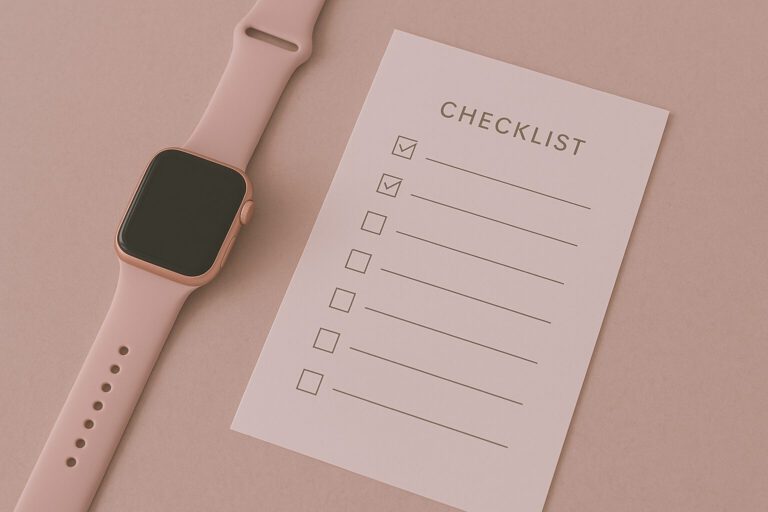「夜になると眠れない」「朝起きてもスッキリしない」
そんな悩みを抱えている方へ、見落とされがちな原因のひとつが、寝室の“光”=照明環境です。
実は、寝る前の光の刺激は、あなたの“脳と体の眠りのスイッチ”を大きく左右します。
この記事では、科学的根拠に基づいた「照明と睡眠の関係」を解説しながら、今日から実践できる照明改善法も紹介していきます。
■ 光と睡眠の関係|なぜ照明が眠りに影響するのか?
私たちの身体には、「体内時計(サーカディアンリズム)」が存在します。これは、朝に活動を始め、夜に休息を取るという生理的なリズムです。
このリズムを調整している最大の要素が「光」です。
▼ ポイントは“メラトニン”というホルモン
メラトニンは睡眠を促すホルモンで、夜に暗くなると分泌が始まり、自然な眠気を誘います。
しかし、夜間に明るい光を浴びると、このメラトニンの分泌が抑制されてしまうため、寝つきが悪くなり、眠りが浅くなってしまうのです。
■ 科学的データで見る「照明の種類と睡眠の質」
以下のように、照明の「色温度」や「明るさ」によって、睡眠の質に差が出ることが多くの研究で示されています:
| 照明の種類 | 色温度 | 影響 |
|---|---|---|
| 白色蛍光灯 | 5000K〜6500K(青白い) | メラトニン抑制・脳が覚醒モード |
| 電球色LED | 2700K前後(暖色系) | リラックスを促し、副交感神経を優位に |
| 間接照明(スタンド・フロアライト) | 2000〜3000K | 光が目に直接入らず、安心感を与える |
特に「青白い光(スマホ・PC・蛍光灯など)」は、夜間の睡眠ホルモンを著しく妨げます。
■ 寝室照明を整えるための3ステップ
ステップ①:主照明から間接照明に切り替える
天井から照らすシーリングライトをやめて、スタンドライトや間接照明を中心に使用するだけでも、寝る前のリラックス度が大きく変わります。
ステップ②:色温度を電球色(2700K以下)に統一
「白くて明るい光」は朝のリビングや仕事部屋には適していますが、寝室では暖かみのある色の光(オレンジ〜暖白色)にするのがベスト。
ステップ③:光の“方向”を下向きにする
光が目に直接入らないようにすることで、脳への刺激を最小限に抑えることができます。
目線の高さ以下に配置されたスタンドライトや、壁を照らす間接照明が理想です。
■ 照明だけで睡眠が変わった!体験談
筆者も以前は、夜遅くまで蛍光灯+スマホを使い続け、寝付きの悪さと朝の疲労感に悩んでいました。
あるとき、思い切って「寝室の照明をすべて電球色のスタンドライトに変更」。
さらにスマホの使用を就寝1時間前にやめたところ、3日目には「自然と眠くなる感覚」が戻ってきたのを実感。
照明の改善は、薬やサプリに頼らず、しかも一度整えればずっと効果が続く「環境投資」といえます。
■ スマホ・TVの光も見直そう
部屋の照明を整えても、就寝直前までスマホ・テレビを見ていると台無しになってしまいます。
▼ おすすめ対策
- ・iPhone → Night Shift モードをオン
- ・Android → ブルーライトカット設定
- ・PC → f.lux や Night Light(夜間モード)を活用
- ・就寝1時間前からは「情報から離れる時間」に
視覚の刺激を減らすことで、「自然に眠れるリズム」が少しずつ整っていきます。
■ まとめ:光を制する者が、眠りを制す
私たちの脳と身体は、原始時代からずっと「日が沈んだら休む」というリズムで動いています。
現代社会の光に囲まれた生活は、便利さと引き換えに“眠りのリズム”を崩してしまっているのかもしれません。
だからこそ、今日から取り入れたい習慣は――
- ・寝室照明は電球色に
- ・直接照らさず、間接照明を活用
- ・スマホやPCの光も見直す
これだけでも、睡眠の質は確実に向上していきます。